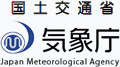2.1 平均相対湿度の長期変化傾向
概要
|
| (注1)ここでは、平成28年度調査時の観測地点において、観測地点を中心とした半径7kmの円内における人工被覆率(平成28年度版国土数値情報土地利用3次メッシュ(1kmメッシュ)における建物用地、道路、鉄道、その他の用地の占める割合)を都市化率と定義しています。 |
平均相対湿度の長期変化傾向
| 地点 | 都市化率(%) | 平均相対湿度変化率 (%/100年) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||
| 札幌 | 71.9 | -11.5 | -10.3 | -12.0 | -10.1 | -13.6 |
| 仙台 | 74.4 | -7.9 | -8.9 | -8.9 | -5.8 | -8.2 |
| 横浜 | 56.0 | -11.7 | -15.9 | -11.1 | -7.9 | -12.2 |
| 名古屋 | 88.5 | -15.4 | -15.2 | -16.6 | -13.2 | -16.7 |
| 京都 | 63.1 | -14.0 | -12.9 | -15.6 | -12.4 | -14.5 |
| 福岡 | 67.7 | -13.3 | -13.3 | -15.1 | -10.2 | -14.5 |
| 13地点平均 | 16.7 | -4.8 | -4.7 | -6.1 | -4.1 | -4.6 |
| 数値ファイル(csv形式) | 平均相対湿度変化率 |
100年あたりの変化率を示す。統計期間は1927年から2023年まで(冬は1926年12月/1927年2月~2022年12月/2023年2月)。都市ごとに、一年で最も変化傾向の大きい季節の数値を赤字、最も変化傾向の小さい季節の数値を青字で示している。なお、大都市11地点中の5地点(東京、新潟、大阪、広島、鹿児島)及び都市化の影響が比較的小さいとみられる15地点(注3)中の2地点(飯田、宮崎)は、観測場所の移転に伴う影響を除去することが困難なため、比較対象から除いている。
(注2)表中の統計期間は、国内主要都市の統計値が揃う1927年以降としています。
(注3)全国の地上気象観測地点の中から、観測データの均質性が長期間確保でき、かつ都市化等による環境の変化が比較的小さい地点から、地域的に偏りなく分布するように選出した15地点(網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木、飯田、銚子、境、浜田、彦根、多度津、宮崎、名瀬、石垣島)。ただし、これらの観測点も都市化の影響が全くないわけではありませんが、同じ15地点の平均から算出される日本の平均気温の上昇率は、日本近海の海域を平均した年平均海面水温の上昇率**と同程度の値であり、都市化の影響が比較的小さいと考えられます。(**1908~2023年までのおよそ100年間にわたる日本近海における海域平均海面水温(年平均)の上昇率は、+1.28°C/100年(気候変動監視レポート2023))
各地点のデータ及び月別の変化
解説
平均相対湿度の100年あたりの低下率は、都市化の影響が比較的小さいとみられる13地点平均の年平均で4.8%であるのに対し、都市化率(注1)の大きい都市ではそれより大きくなっています。季節別で見ると、低下率が最も大きい季節は都市によって異なるものの、低下率が最も小さい季節は夏、特に梅雨時期(月別では6月や7月の低下率が最も小さい)である都市が多くなっています(4.11 大都市及び都市化の影響が比較的小さいとみられる13地点平均の月平均相対湿度の長期変化傾向(表)参照)。これは、梅雨時期は曇りや雨の日が多く、都市化の影響が現れにくいためであると考えられます。また、都市における相対湿度の低下の要因としては、気温の上昇に伴う飽和水蒸気圧(大気中に含みうる水蒸気量の最大値)の増加によって相対湿度が下がる効果が主であると考えられますが、都市域では植物が少なくなり、蒸発散が弱くなるために水蒸気そのものが減少する傾向も寄与している可能性があると指摘されています(藤部, 2012a, 2012b)。
参考文献
- 藤部文昭, 2012a: 都市の気候変動と異常気象 猛暑と大雨をめぐって. 朝倉書店, 176pp.
- 藤部文昭, 2012b: 観測データから見た日本の都市気候. 気象研究ノート, 224, 1-23.